みなさん、「帰納法」って言葉を聞いたことはあるけどよくわからない、使い方を知りたいと思ったことはないでしょうか。「きのうほう」と呼ぶ思考法について、ご紹介しようと思います。
この記事では、帰納法とは何か、例題も含めてわかりやすく解説します!
以前、公開した「演繹法」の記事も合わせて見てみてください!
では早速本題です。
帰納法とは?

結論、帰納法とは「ある事柄をたくさんの傾向・情報から考えて、解決策や対策を考える」といった思考法のことです。
ウィキペディアでは以下のように定義されています。
さまざまな事実や事例から導き出される傾向をまとめあげて結論につなげる論理的推論方法を指します。別名を「帰納的推論」ともいいます。
帰納法の定義は難しく聞こえますが、日常でもかなり頻繁に起こる事例であり、自然と思考していることかと思います。
先日公開した「演繹法」は、「ある事柄を今までの傾向から考えて、解決策や対策を考える」です。
合わせて読んでみてください!
帰納法の例
それでは、帰納法の例を考えてみます!
1、事柄:メールにて友人A、B、C君を飲み会に誘ったが、来てくれなかった。
帰納:メールで誘っても来てくれない。
2、事柄:サッカー部に新入生を20人ほど入れたいが、一昨年は5人で昨年は9人、今年は8人しか集まっていない。バスケ部は毎年15人ほど入部している
帰納:サッカー部よりもバスケ部の方が魅力的に写っている。
3、事柄:飲食店の集客にて、3週間連続で水曜日の集客数が一番低い数値だった。
帰納:水曜日は集客数を見込めない曜日。
などなど。意外とシンプルではないでしょうか。
もちろん事例がざっくりとしているため、かなりアバウトな説明ではありますが、帰納法の概念としてはこのような感じだということですね。
実際のビジネスや日常生活で活かすポイントを解説していきます!
帰納法を使う上でのポイントと注意点

帰納法を使う上でのポイントは、見逃している他の要素(反証例)を考慮しているかチェックすることです。
帰納方的に導き出されることとして、例えば上の例にも出したメールで友人を誘ったが断られた例ですが、帰納法的に考えた際に、
・メールを送った時間がそもそも通知に気づかない時間の可能性
・誘う際の文章がわかりづらい、硬い
・誘った日にちに問題がある
など、複数個の要素が考えられます。
あくまで、たくさんの傾向・情報から考えて、解決策や対策を考えるということが前提なので、抜け漏れをチェックする段階が重要です。
また、状況の変化が激しい事象を帰納的に考える際は、変化に伴った思考ができているか見つめ直しましょう。(これは演繹法も同じですね!)
まとめ

まとめです!
帰納法とは「ある事例をたくさんの傾向・情報から考えて、解決策や対策を考える」といった思考法のこと。
帰納法を使う上でのポイントは見逃している他の要素(反証例)を考慮しているかチェックすること。
帰納法の注意点としては、状況の変化が激しい事象を帰納的に考える際は、変化に伴った思考ができているか見つめ直すこと。
内容は以上になります!
帰納法を知る上で参考になった書籍を貼っておきますね!
また、「演繹法」についての記事はこちら!
それではまた!!
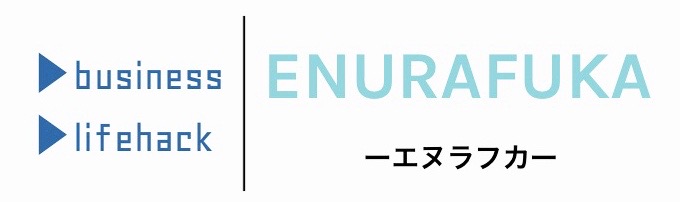



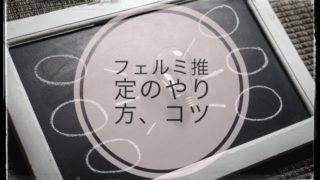


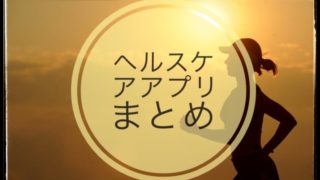

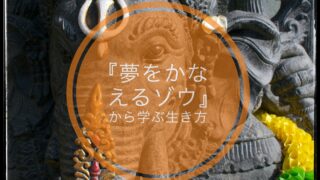
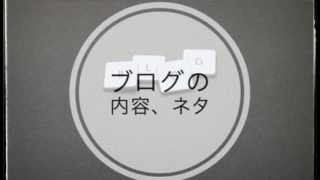




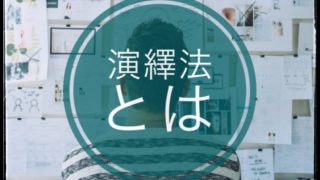


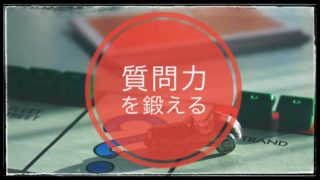
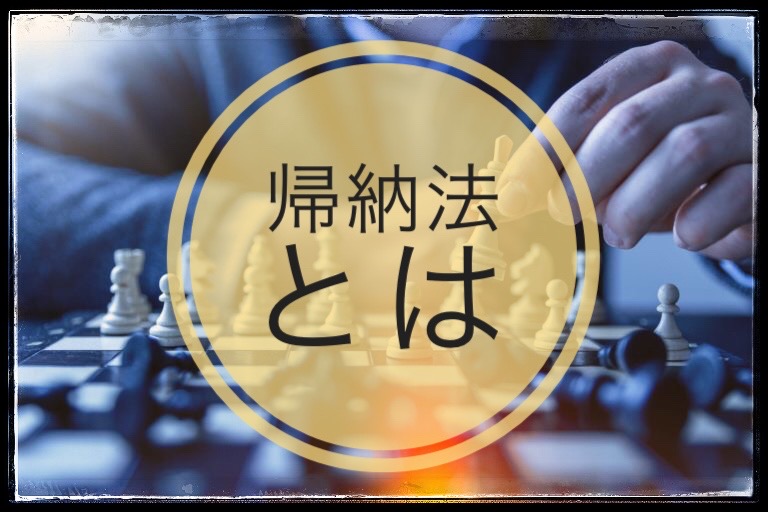




コメント